![]()
![]()
ここでは、修論の概要に書いたことを載せています。
修士論文には、論文本体と概要の2つがありますが、本体は40ページ以上もある
巨大なデータのため、このページには概要の方を載せています。
修士論文本体は次からダウンロードできます。(Word2000形式)
C60に対してアルカリ金属であるRbを1:1でドープさせたRb1C60は、350K以上の高温でC60がfcc構造をとっているNaCl構造になる。(Fig. 1の左) これを350Kから徐冷すると、300K付近でC60分子がa軸方向で縮み一次元的に結合したorthorhombic構造を持つ、フラーレンポリマーになることが知られている (Fig. 1の右) 。
1次元のポリマー化したRb1C60の性質として、比較的高い電気伝導度を持っており、常圧,約50Kで反強磁性転移が起こることが知られている。この現象の解釈として、1次元金属のFermi面にエネルギーギャップが開くSDWであるという提案がされている。一方で理論的な計算では、鎖間での電子のオーバーラップも重要であることが分かり、3次元的な電子状態が提案されている。そこで、Rb1C60の圧力下での電子状態の変化をEPRで観測することを目的とし、測定を行った。
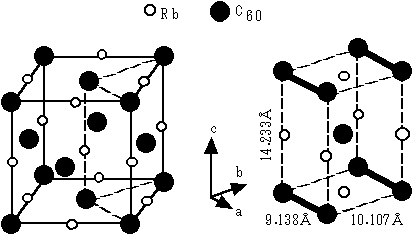
Fig. 1 Rb1C60の分子モデル
Rb1C60の磁化率をEPR測定装置によって観測することで、Neel温度の圧力変化を得ることができた。この結果と、K.Khazeniらによって測定されたRb1C60の電気抵抗の結果を統合すると、Fig. 2に示すような相図ができる。今までいわれていた1次元金属のFermi面にエネルギーギャップが開くことによって安定化されるSDWが基底状態であるという考え方では、T> TNではフェルミ面を持つのでMetal、T< TNでは反強磁性になりフェルミ面にギャップが開くのでInsulatorになると予測される。しかし、AFM(反強磁性金属相)とPI(常磁性絶縁体相)の2つの相が現れることは、この考え方では矛盾が生じる。そこで、AFI、AFMの相を持ち得るMott-Hubbard系と見比べてみると似ていることが分かった。これをエネルギーの観点から考察していく。加圧前はFig. 3の左に示すように、電子は下のHubbardバンドに詰まっている。上のHubbardバンドの間にはエネルギーギャップがあるため、絶縁体として振る舞う。一方、加圧すると格子間隔が縮まるため、Hubbardバンドが広がっていく。ある圧力を越えるとFig. 3の右に示すように上のHubbardバンドと下のHubbardバンドが重なりフェルミ面が現れるので、金属として振る舞う。
次にEPR線幅について考察する。温度が50K以上の部分に着目すると、Metalになったと考えられる圧力では電気抵抗との間に強い相関があることから、この電子系はElliott機構によって決まっていると考えられる。加圧すると、Fig. 3のように格子間隔が縮まるため電子のエネルギーバンドが広がる。同様にしてRbの電子軌道のエネルギーバンドも広がるため、Rb軌道と電子とのエネルギーギャップΔEは図の通りに縮まると期待される。この影響によってEPR線幅に関係するΔgの値が変化するので、EPR線幅が増大することが期待される。このようにしてEPR線幅が圧力と共に広がる理由を、Elliott機構によって矛盾なく説明することができた。
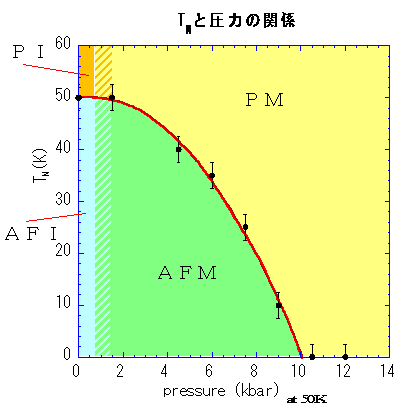
Fig. 2 Rb1C60の相図
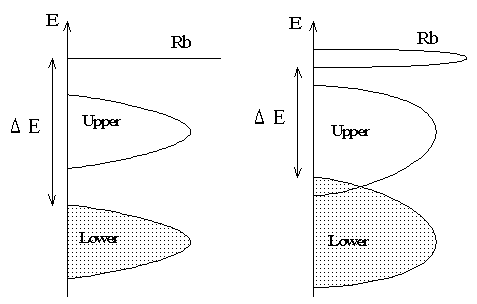
Fig. 3 圧力によるエネルギーバンドの変化